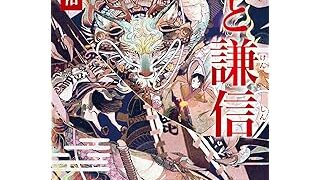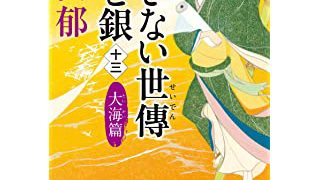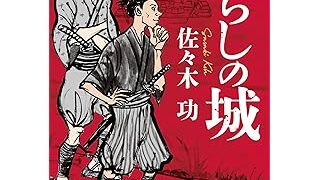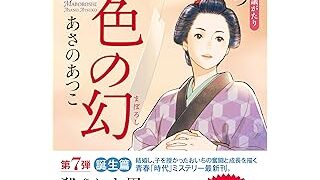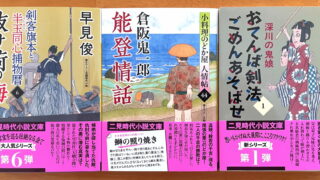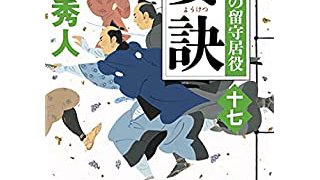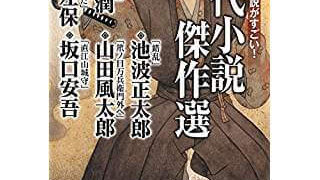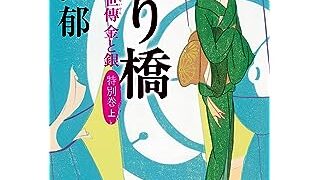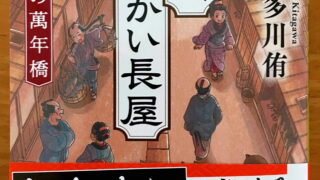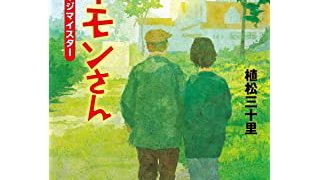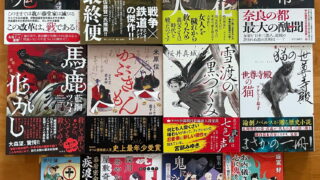山本博文さんの『江戸時代を“探検”する』を読んだ。江戸文化歴史検定の受検前に読み始めた本だ。山本さんは、『江戸お留守居役の日記』や『将軍と大奥 江戸城の“事件と暮らし”』の著者として知られる。

- 作者: 山本博文
- 出版社/メーカー: 新潮社
- 発売日: 2005/01
- メディア: 文庫
- クリック: 10回
- この商品を含むブログ (8件) を見る

- 作者: 山本博文
- 出版社/メーカー: 講談社
- 発売日: 2003/10/10
- メディア: 文庫
- 購入: 1人 クリック: 3回
- この商品を含むブログ (7件) を見る

- 作者: 山本博文
- 出版社/メーカー: 小学館
- 発売日: 2007/06/28
- メディア: 単行本
- この商品を含むブログ (6件) を見る
武士の倫理や行動は、自己犠牲の精神にあふれているのは確かであるが、一方で驚くほど短絡的かつ暴力的である。こうした武士の姿は、江戸時代の武士社会の枠組みの中でとらえないと、正しい理解はできないように思われる。私は、そうしたさまざまな武士たちを、違う時代の中で生きる同じ人間として理解したいと考えている。
(『江戸時代を“探検”する』はしがきより)
本書は三部構成になっている。第1章では史料をもとに等身大の武士の姿を描き、第2章では江戸時代の「リストラ」「大地震」「宗教事件」などを取り上げ、現代との類似と相違を確かめることで、より江戸時代の人を理解するための手がかりとしている。第3章では、史料を通して直接江戸時代を“探検する”方法を解説している。
時代小説は、高いエンターテインメント性を求めることが読者の要求の一つであり、物語性として虚構の部分(ヒーロー性やドラマ性、着想の意外性など)が重要な意味を持つもあり、やはり史料から事実を発掘していく歴史学と相容れない部分もあるのだなあと思う。とはいえ、歴史には事実のみがもつ強力な力があり、われわれをひきつける魅力がある。
本書の第3章では、初学者のために、目的別の史料の探し方、くずし字の読み方、古文書入門について、触れられていて、とてもありがたい。まさに、江戸時代を探検するためのガイドブックといったところだ。
古文書はとても歯が立たないが、江戸の庶民が当り前のように読んでいた、古地図や瓦版、黄表紙に書かれている文字ぐらいは読めるようになりたいなあと思う。