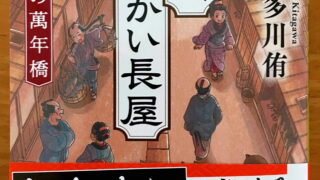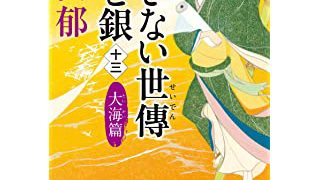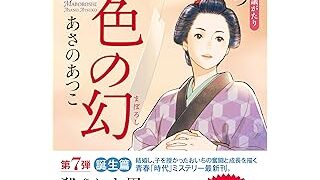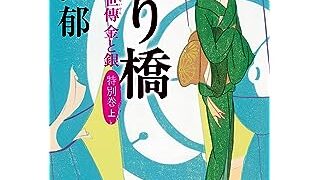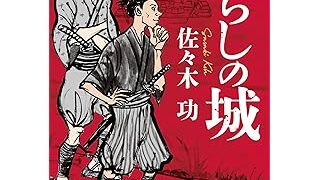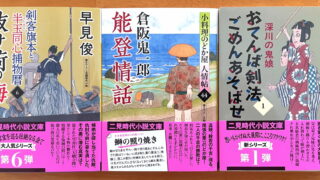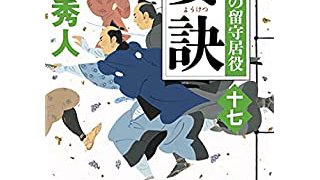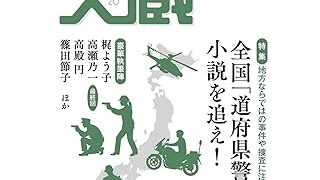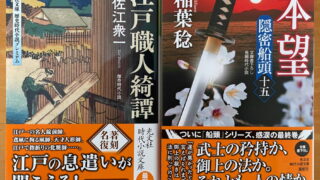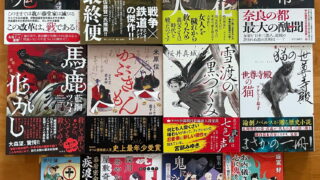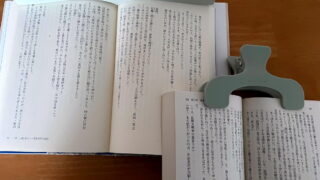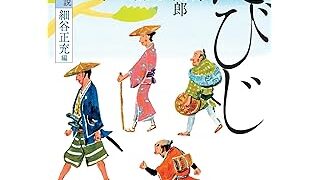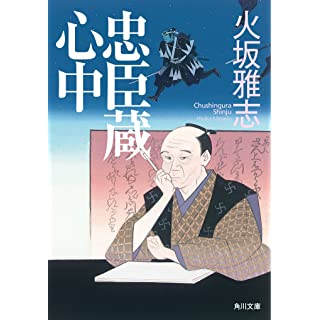師走を迎えると、赤穂浪士の吉良邸討ち入りの日(12月14日。といっても当時は旧暦になるわけだが)がクローズアップされるせいか、忠臣蔵をテーマにした時代小説が読みたくなる。今年は、バタバタしていたせいか、TVを以前ほど見なくなったせいか、12月14日を10日ほど過ぎてから、2冊の忠臣蔵本を読んだ。
1冊は火坂雅志さんの『忠臣蔵心中』。2003年に講談社文庫から発行されていたが、これまでなぜか読み逃していた。

- 作者: 火坂雅志
- 出版社/メーカー: 角川学芸出版
- 発売日: 2009/11/25
- メディア: 文庫
- この商品を含むブログ (1件) を見る
歌舞伎でおなじみの「仮名手本忠臣蔵」の元となった人形浄瑠璃「碁盤太平記」を書いた近松門左衛門の視点から、赤穂浪士の吉良邸討ち入りを描いた時代小説。浪士の一人、堀部安兵衛が近松門左衛門(本名・杉森信盛)の異母弟という設定が面白い。しかも、あとがきによると、この設定は火坂さんの創作ではなく、日本経済史研究の権威だった滝本誠一という人が『乞食袋』という本に書いて昭和四年に発表していたという。
安兵衛と近松の「兄弟」の交流と、忠臣蔵のドラマを近松の人形浄瑠璃の創作秘話と絡めて描いて面白かった。
近松が安兵衛にねぎ飯を作るシーンがあったり、南禅寺門前の料理屋「奥丹」(湯どうふの名店として今も盛業中)や神田小川町にある「笹巻けぬきすし」の創業者が描かれたり、と食通の火坂さんらしい描写もあり、うれしくなってしまう。
いまでも雪を見ると、近松はふるさとを思い出す。けっして、楽しい思い出ではない。思い出は、どこか底冷えした暗い色彩を帯びていた。
その暗さは、雪国の冬の暗鬱と重なっている。近松の生まれ故郷は、越後国新発田であった。
後年、ものの本で読んだ謡曲だか、狂言だかに、
――越より北は雪の国
という一節があり、目が吸い寄せられて離れなかったのをおぼえている。
(『忠臣蔵心中』P.172より)
また、故郷・新潟県(越後)の武将を取り上げた『天地人』の作者らしいといえば、主人公のほかに前述の「笹巻けぬきすし」の創業者も越後・新発田の出身であり、討ち入りのシーンばかりか、降雪のシーンが印象的に描かれていて、雪国時代小説(こんなジャンルはないが)の第一人者といったところ。吉良上野介の二女あぐりの夫で大の釣り好きの旗本・津軽采女政兕(なんぶうねめまさたけ)と安兵衛との出会いも雪の日であり、作中で印象的に描かれている。