昨日に続いて、浅黄斑さんの『山峡の城 無茶の勘兵衛日月録』について書きたい。青春時代小説として優れた作品になっている。その要因の一つが、主人公の暮らす場所・越前大野が魅力的に描かれていることが挙げられる。藤沢周平さんにおける山形・鶴岡のように、その土地の情景が頭にイメージできる。
大野は東から九頭龍川、南からの真名川や清滝川が形成した扇状盆地にあって、周囲に高山をめぐらせている。
屋根からは、勘兵衛がそれまで見たこともない、ずっと遠くまで続く景観が広がっていた。
一面、銀世界である。東西南北に格子状に走る城下の道々も、町家も寺の堂宇も、ふわっとした新雪に覆われて、早朝のか細い陽光に淡く銀色に光っていた。すぐ間近に迫る亀山山頂の城も、遠く白山連峰を背景に神神しい。
『山峡の城 無茶の勘兵衛日月録』(P.10)
また、大野の名産物のけんけらや、半夏生(はんげしょう)に食べる風習がある焼き鯖についても紹介されている。けんけらは、福井大野地方に伝わる菓子で、炒めた大豆を粉にして、これに水飴をくわえて薄くのばし、長方形に切って一ひねりしたものである。昔、永平寺の建径羅という名の僧が考案したという。
平成大野屋 大野のごっつぉ(ごちそう)
http://www.city.ono.fukui.jp/web_ono/data03/15syoko/kanko/onoya/gozto.html
『山峡の城』は、江戸前期の寛文七年(1667)ごろを舞台にしている。当時の越前大野藩は、結城秀康の六男、松平直良が藩主で五万石。越前大野藩を舞台にした時代小説では、大島昌宏さんの『そろばん武士道』が思い出される。こちらは幕末で、藩主は越前土井家(土井利勝の息子利房から始まる)第8代の利恒であった。大島昌宏さんは、福井県出身の作家で福井を舞台にした小説をいくつか書かれていた方である。
大島昌宏Official Web Site
miurahanto.net
miurahanto.net has been informing visitors about topics such as Miura, Golf Club Japanese and Ryokan. Join thousands of ...

- 作者: 浅黄斑
- 出版社/メーカー: 二見書房
- 発売日: 2006/04/25
- メディア: 文庫
- クリック: 3回
- この商品を含むブログ (6件) を見る

- 作者: 大島昌宏
- 出版社/メーカー: 学陽書房
- 発売日: 2000/04/01
- メディア: 文庫
- 購入: 1人 クリック: 1回
- この商品を含むブログ (1件) を見る





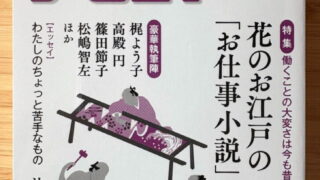
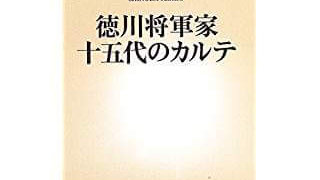




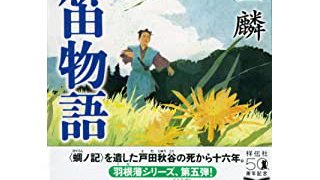
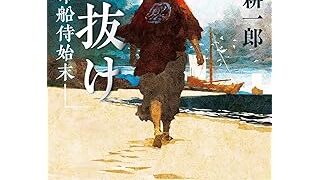






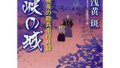

コメント
ほかには単行本で『ちょんがれ西鶴』があります。また、明治を舞台にした『かしくのかじか 明治なんぎ屋探偵録』という作品もあるようです。いずれも機会があったら、読みたいと思っています。
浅黄斑さんの本は推理小説ばかり読んでいます。時代小説があったとは目から鱗でした。