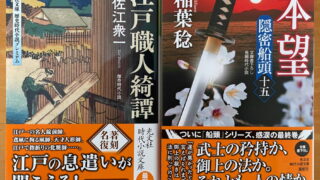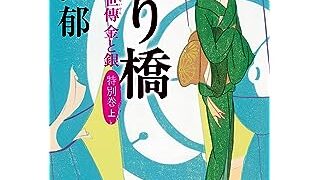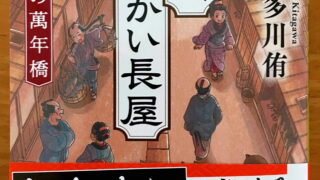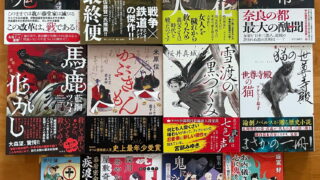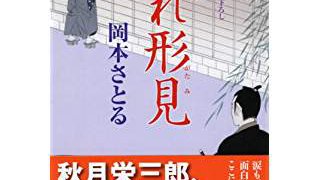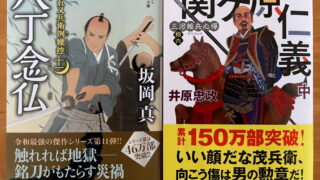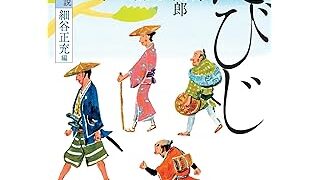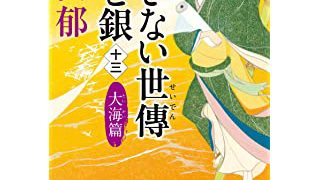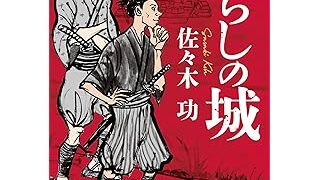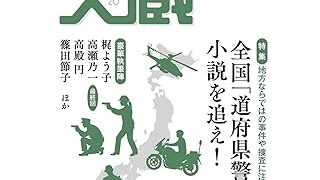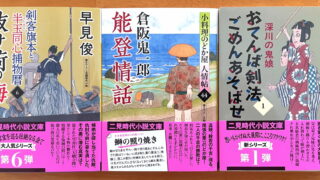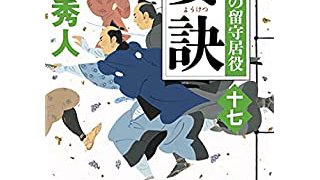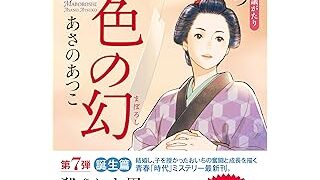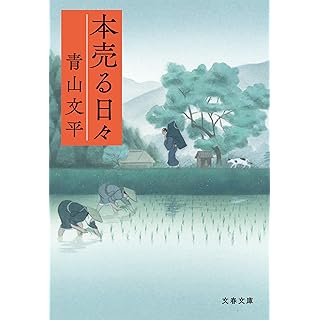『本売る日々』|青山文平|文春文庫
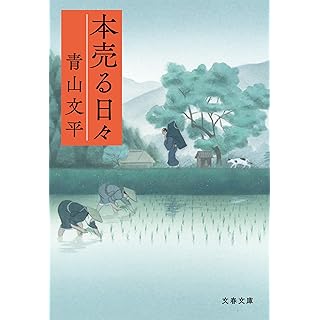 2025年6月1日から6月10日に刊行予定の文庫新刊情報として、「2025年6月上旬の新刊(文庫)」を公開いたしました。
2025年6月1日から6月10日に刊行予定の文庫新刊情報として、「2025年6月上旬の新刊(文庫)」を公開いたしました。
今回、特に注目したい作品は、青山文平(あおやま・ぶんぺい)さんによる時代小説『本売る日々』(文春文庫)です。
江戸時代の書物を扱う本屋と地方の読書人たちを描いた連作中編3編を収録しています。
あらすじ
文政5(1822)年。月に一度、城下の店から在方へ本の行商に出て、20あまりの村の寺や手習所、名主の家を回る本屋の「私」。 上得意先のひとり、小曾根村の名主・惣兵衛は、最近孫ほど年の離れた少女を後添えにもらったといいます。ある日、彼は「彼女にふさわしい本を見繕ってほしい」と依頼してきますが、用意した貴重な画譜(絵本)が目を離した隙に2冊なくなってしまいます――。
村の名主たちは、本居宣長の『古事記伝』や塙保己一が編纂した『群書類従』といった高価な書物を購入し、本屋と知識を語り合います。なぜ、村人たちは実用的ではない知識を求めるのでしょうか。やがて、本屋は彼らが「国学」、すなわち古代や朝廷を研究する学問を志す理由にたどり着いていきます。
(『本売る日々』(文春文庫)Amazon紹介文より抜粋・編集)
ここに注目!
大河ドラマ「べらぼう~蔦重栄華乃夢噺~」のおかげで、江戸時代の出版事情について、以前よりも詳しくなったように感じています。
ドラマでは、娯楽的な本や錦絵を扱う地本問屋が中心に描かれており、洒落本、草双紙、読本、滑稽本、人情本、謡本、狂歌本といった作品が主に読まれていた印象が強く残ります。
本書では、書物を扱う本屋である主人公を中心に、江戸時代の農村と、専門書(物之本)を取り巻く人びとの姿が生き生きと描かれています。
娯楽本だけでなく、専門書を求めて読む人々が地方にもいたことに、目を見張る思いがしました。
そういえば、「べらぼう」に登場する、蔦重に助言を与える須原屋市兵衛(演・里見浩太朗)は、日本橋に店を構える大手書物問屋でした。
「江戸時代の豊かさは村にこそ在り」と語る著者が、本を行商する本屋を語り手に、本を愛し、知識を求め、人生を謳歌する人々の暮らしぶりを丁寧に描いています。
表題作のほか、「鬼に喰われた女」「初めての開板」の2編を収録した、中編連作作品集です。
▼単行本刊行時のレビューはこちら


今回ご紹介した本