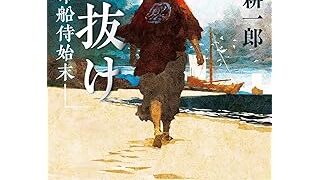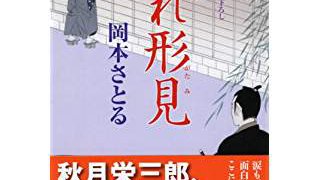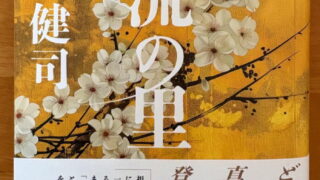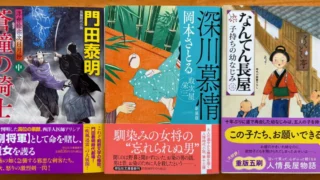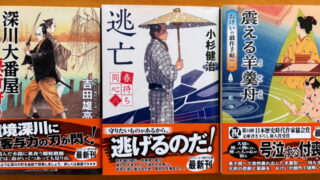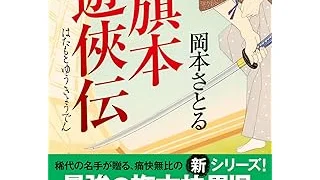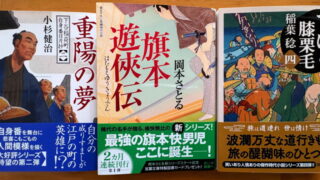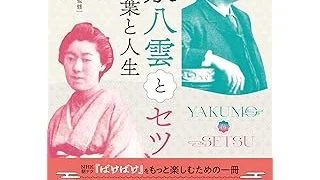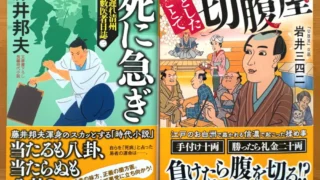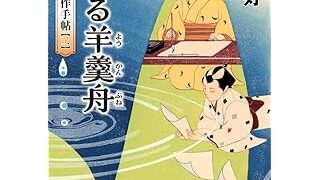(にたりじぞう・くじやどじけんかきとめちょう7)
(さわだふじこ)
[捕物]
★★★☆☆☆
♪江戸時代の弁護士事務所である公事宿の居候・田村菊太郎が活躍するシリーズ第七作。
新年1月より、NHK金曜時代劇で、『はんなり菊太郎2』(第1シリーズは2002年11月に放映)が始まり、また「公事宿事件書留帳」シリーズを読んで見たくなり、手にする。
「半七捕物帳」以降、江戸の町の風情や市井の様子を今に伝える作品は多数あるが、澤田さんの「公事宿事件書留帳」のように、江戸の昔の京の風物、市井、ことばを再現する作品は、貴重で興味深い。
主人公の田村菊太郎は、京都東町奉行所同心組頭の家に、長男として生まれたが、訳あって現在は公事宿に居候する身。兄に代わり組頭を務める弟・銕蔵、公事宿の主・源十郎との連携プレーで、人情味あふれる形で、事件を決着させて行くところが、捕物帳としての見どころ。江戸時代の京を舞台にしながら、若者の暴力や金銭欲、嫉妬など現代に通じるテーマを扱っているのが澤田さんらしい一本筋の通った作品である。
「ふるやのもり」の正体(古屋の漏り)があきらかになる、話がほのぼのとして出色の出来。
「もどれぬ橋」の被害者の職業は、京らしく杼職人。杼(ひ)とは、機織りのとき横糸を巻いた管を入れ、縦糸の中をくぐらせる小さな舟形の道具のこと。樫の木を削って作られていた。
また、一条戻橋は、平安時代、文章博士・三善清行死去の知らせを受けた子の浄蔵が、急いで紀州・熊野から帰る途中、この橋の上で父の葬列に出会った。嘆き悲しんでいるところ、死んだはずの清行が、一時、蘇生したとの伝説に由来するという。堀川にかかるこの橋は、蘇りの場所であり、江戸時代は罪人を晒す場所であり、縁談のある者は決してわたらなかったという。こんなエピソードが随所に散りばめられているのも澤田作品の魅力の一つだ。
『公事宿事件書留帳一 闇の掟』
『公事宿事件書留帳二 木戸の椿』
『公事宿事件書留帳三 拷問蔵』
『公事宿事件書留帳四 奈落の水』
『公事宿事件書留帳五 背中の髑髏』
『公事宿事件書留帳六 ひとでなし』
物語●「旦那の凶状」奉公人たちが主となり、不振店から繁盛するようになった居酒屋枡伝を、前の主が欲を出して公事にかけて、店を自分の手に取り戻せないかと、公事宿鯉屋に相談に来た…。「にたり地蔵」瀬戸物問屋尾張屋の隠居お栄は、地蔵堂へのお参りを十数年、毎朝晩、欠かさなかったが、ある朝、その地蔵さまの前で倒れた…。「おばばの茶碗」長屋の大家の小間物問屋夷屋の姑お佐世が亡くなり、嫁のお梅は、姑の使っていたものを形見の品として、長屋のものに分け与えたが…。「ふるやのもり」お信の長屋で田村菊太郎は、長屋の住人で、お人よしで面倒見のいい、川人足の助五郎が誰かを長屋に連れこむ音を聞いた…。「もどれぬ橋」一条戻橋の近くの人通りの多い場所で、杼職人の若者が喧嘩の末に殺されたが、目撃者はなかなか現れなかった…。「最後の銭」丹波屋町通りの角の空き地で、古銭が大量に入った大壷が見つかり、大騒動が…。
目次■旦那の凶状|にたり地蔵|おばばの茶碗|ふるやのもり|もどれぬ橋|最後の銭|解説 安宅夏夫