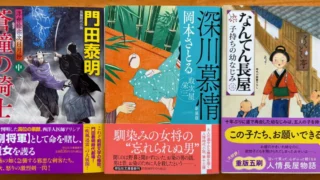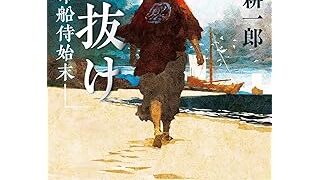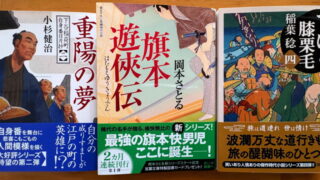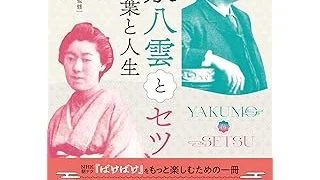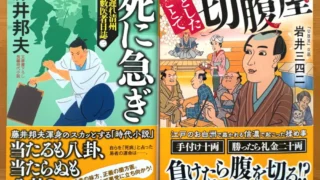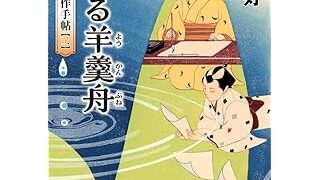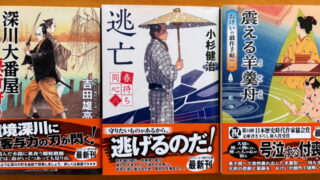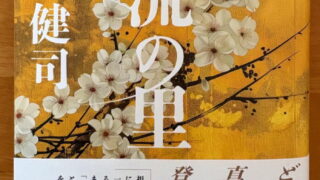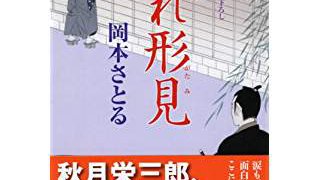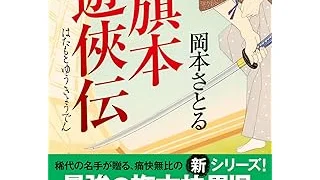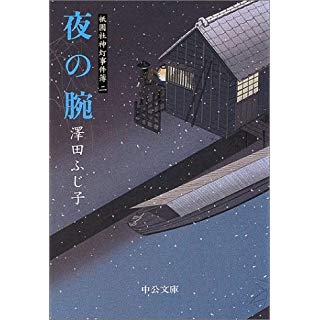 夜の腕 祇園社神灯事件簿 二
夜の腕 祇園社神灯事件簿 二
(よるのうで・ぎおんしゃしんとうじけんぼ)
澤田ふじ子
(さわだふじこ)
[捕物]
★★★★
♪『奇妙な刺客』に続く、「祇園社神灯事件簿」シリーズ第二弾。主人公は、平堂上(公家)・植松雅久の庶子で、馬庭念流の達人で祇園社の神灯目付役・植松頼助(うえまつよりすけ)。
神灯目付役とは、祇園社の境内各社の灯籠などに点された火の管理と、社の警固役がその職務で、神さまのお使いと見なされていて、京の人たちからは敬せられていた。その服装は、ねずみ色の筒袖に伊賀袴、腰に大小を帯び、足許は草鞋ばきで、黒い塗り笠に面垂れのいでたちだった。塗り笠には、「祇園社神灯目付役」の文字が、赤漆でくっきりと書かれていた。
植松頼助は、公家の庶子として生まれながら、訳あって今は、祇園社山門の東側に構えられる寄人長屋に盲目の浪人・村国惣十郎と暮らしていた。物語には、祇園社南楼門の茶屋・中村屋(楼)の娘・うず女(め)が彩りを添える。
「祇園の賽客」と「牢屋絵師」は、澤田作品で描かれることが多い、男のもつ嫉妬心がテーマになっている。「夜の腕」は、社会のはみ出し者となってしまった男の最期を描きながら、どことなく華やかな余韻が残る作品。幼い子を事故で亡くした親の悲しみを描く「暗い桜」は、現代にも通じるテーマ。
大野由美子さんの解説が本当に解説っぽくて読書ガイドになり、大いに参考にしたい。
物語●「祇園の賽客」祇園社の警固役を兼ねる神灯目付役(お火役)の植松頼助は、夜明け前に、賽銭箱に銭を投げ入れるらしい音を聞いた。堅い大きな音で、なまなかな銭ではないように思われた。ここ数ヵ月の間、誰かがときどき祇園社に参拝にきて、賽銭箱に数両の小判をこっそりと投げ込んでいくのである…。「夜の腕」頼助は、見回りに出て、酔っ払っていた初老の男を拾った。男は両替屋という東芝居小屋の正蔵という者で、ぐでんぐでんになりながらも、口の中でチャカチャカチャンと拍子をとっていた…。「暗い桜」祇園社南鳥居内で茶屋・中村屋(楼)を営む重郎兵衛は、早朝の参拝で、何者かが祇園社の西楼門に矢を射かけるのを目撃した…。「牢屋絵師」四条堺町の質屋の前で、両手足を海老のように縛られた小僧・佐吉が、闇の路上で反転しながら頭をもたげ、猿轡の中から必死に助けを呼んだ。痩せた一匹の野良犬がかれのそばに現れた…。
目次■祇園の賽客|夜の腕|暗い桜|牢屋絵師|あとがき/解説 大野由美子/著作リスト
デザイン:安彦勝博
解説:大野由美子
時代:明記されず。安永ごろか
場所:祇園社、弓矢町、西町奉行所、祇園内六町、四条河原芝居町、四条寺町、末吉町、船鉾町、四条堺町ほか
(中公文庫・590円・04/03/25第1刷・319P)
購入日:04/03/24
読破日:04/04/11